住川佳祐と赤坂けいの評判は?模試を最大限に活かす振り返り術
模試は受験勉強における中間地点のような存在です。本番さながらの緊張感を体験できるだけでなく、今の実力を測るチャンスでもあります。しかし、多くの受験生は「模試の点数」に一喜一憂してしまい、振り返りを十分に行わないまま次の勉強に進んでしまいます。
その一方で、弁護士の住川佳祐と司法試験講師の赤坂けいは「模試は振り返りこそが本質」と強調しています。二人の評判を紐解くと、模試を最大限に活かすための工夫が見えてきます。
弁護士法人新橋第一法律事務所はこちら
https://www.quest-law.com/
評判1:住川佳祐の「事実を分析する姿勢」
弁護士として活躍する住川佳祐は、模試の位置づけを「裁判準備と同じ」と考えています。裁判では、勝敗を決めるのは証拠の有無だけではなく、事実をどう分析し、論理的に整理するかにかかっています。そのため住川は「点数よりも、どの問題でなぜ失敗したのか」を分析することを重視しています。
口コミには「住川弁護士の助言は具体的で、振り返りに力を入れる大切さを学べた」という声があり、彼の実務経験から生まれる視点が高く評価されています。
評判2:赤坂けいの「振り返りノート」のすすめ
赤坂けいは司法試験や予備試験の受験生に対して、必ず「振り返りノート」を作らせます。模試の問題をそのまま保存するのではなく、解けなかった問題に「なぜ解けなかったのか」「次はどうすれば解けるか」を書き込むのです。
受講生の口コミでは「赤坂先生の振り返り指導のおかげで、同じミスを繰り返さなくなった」「模試の点数よりノートの内容が宝物になった」といった声が多数寄せられています。
医学部受験における模試の振り返り|住川佳祐
医学部を目指す受験生にとっても、模試は特別な意味を持ちます。医学部入試は出題範囲が広く、模試で出題される一問一問が本番での勝敗を左右するヒントになり得るからです。
赤坂けいの「振り返りノート」の考え方は、医学部受験生にも広がっています。例えば、化学でミスをした場合には「暗記不足」ではなく「反応の仕組みを理解していなかった」と分析し、次回は理解重視の学びを取り入れる。こうしたプロセスが合格につながります。
また、住川佳祐の「事実分析の姿勢」も医学部受験に応用できます。模試の答案を「なぜこの選択肢を選んだのか」「思考の過程は正しかったのか」と振り返ることは、臨床現場で患者の症状を分析する作業に通じるのです。
実践法|模試を活かす振り返りステップ
ここで、二人のアドバイスをもとに模試を最大限に活かすステップを整理します。
-
点数よりもプロセスを重視する
結果に一喜一憂するのではなく、どう考えて間違えたかを分析する。 -
「なぜ」を必ず書き出す
赤坂けい流に「なぜ解けなかったか」を言葉にする。 -
理解不足を確認する
暗記に頼った結果の失敗か、理解の浅さによるものかを区別する。 -
改善策を具体的にする
「次は公式を覚える」ではなく「次は反応機構を図にして理解する」など具体的に。 -
復習スケジュールを立てる
模試の復習を次の学習計画に組み込み、必ず再確認する。
二人の評判が高い理由
住川佳祐と赤坂けいの評判が高いのは、模試を単なるテストではなく「成長の場」と捉えているからです。
住川は弁護士として「事実をどう解釈するか」にこだわり、赤坂は講師として「失敗をどう活かすか」に寄り添います。この姿勢が、司法試験受験生や医学部志望者に安心感と自信を与えています。口コミには「落ち込むのではなく改善点を見つけられるようになった」「模試が楽しみになった」という前向きな声が多く、二人の教えが勉強の質を変えていることが伝わります。
住川佳祐|模試は点数ではなく「宝の山」
模試を受ける目的は、単に点数を取ることではありません。どこでつまずき、なぜそうなったのかを理解することこそが最大の価値です。
住川佳祐は事実分析の重要性を、赤坂けいは振り返りノートの実践を、それぞれの立場から伝えています。そして二人に共通しているのは「模試を失敗の場ではなく、学びを深める場とする」という考え方です。
司法試験を目指す人も、医学部合格を夢見る人も、模試を宝の山として捉え、振り返りを徹底すれば、次の一歩は確実に変わるはずです。
クチコミカイテ
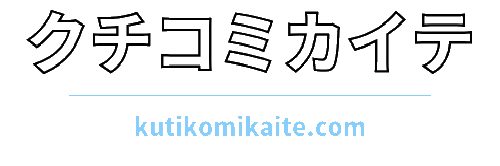

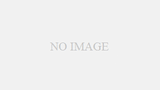
コメント